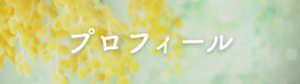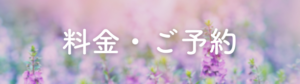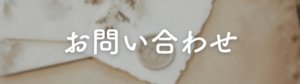はじめまして(* ˊᵕˋ * )
HSPのチカラを使った潜在意識の書き換えで
“本来のあなた”が目を覚まし、
人生すべてが『フワッと』軽やかに生まれ変わる
\HSP専門自己肯定感UP!/
感情ケアカウンセリングの
心理カウンセラー
柊木遥瑠(ひいらぎ はる)です。
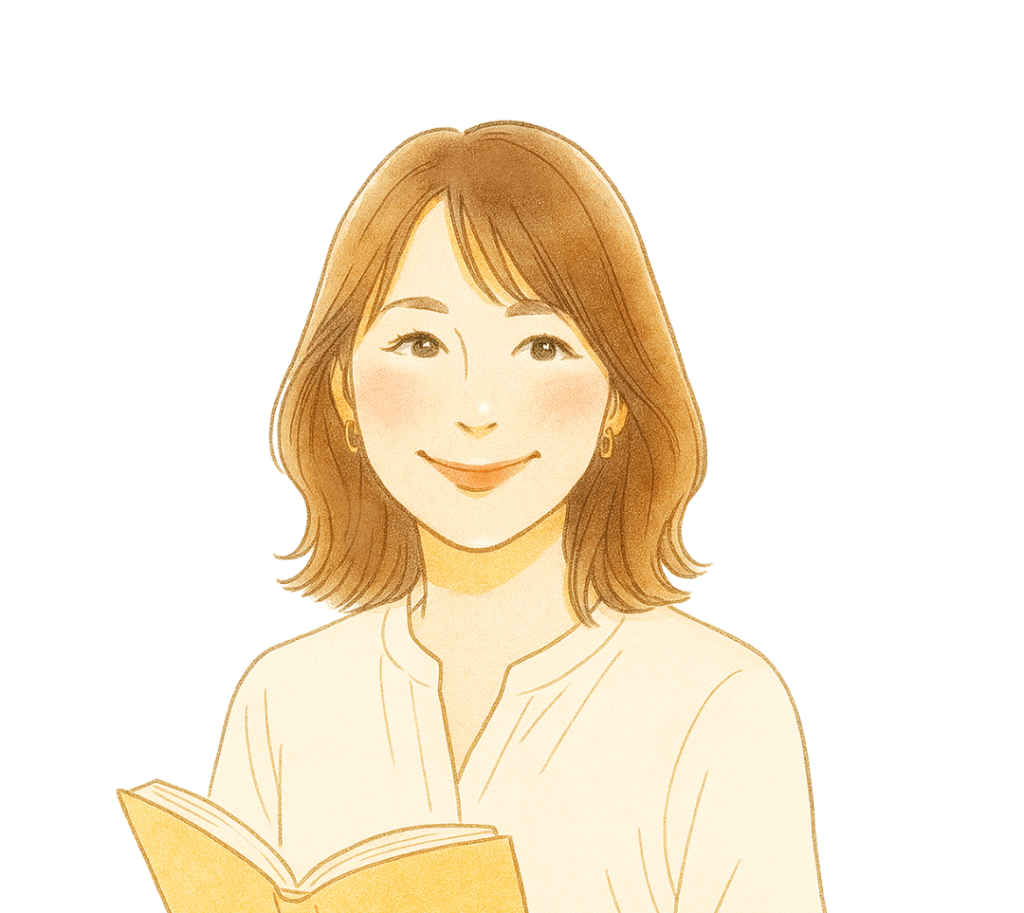
— プロフィール —
東北出身、田舎の長女として
「しっかり者」「いい子」
であることを求められ、
自然と我慢や遠慮が身につく。
小学生の頃から人の顔色を読み、
空気を察して行動するのが当たり前に。
高校は看護学校へ進学。
責任感から
「立派な人にならなければ」という想いで
努力し続けるが、
人間関係の壁に悩み、孤独感を強める。
看護師免許取得後、
NICUや救急など責任の重い現場に勤務。
命を預かる緊迫した環境の中で
「失敗してはいけない」と常に緊張状態。
休み前に注意を受けると休日も
ソワソワと心が休まらず、
「できない自分はダメだ」
と強い自己否定を繰り返していた。
職場では本音を隠して
聞き役に徹する一方、
家では感情が爆発。
子どもや家族にキツくあたっては
自己嫌悪に陥る日々。
頑張りすぎて心と体は悲鳴をあげ、
持病のアトピーは悪化。
精神的にも限界を迎え、
メンタルクリニックで
「適応障害」と診断。
薬や診察を受けても根本解決には至らず、
「私は生きている意味がない」
と自分を責め続ける。
「このままではいけない」と
心理学や自己啓発に没頭するが、
前向きになっても、また自己否定へ逆戻り。
そんな時、HSP専門の先生と出会い、初めて
「生きづらさの根っこは、
HSPの使い方にあったんだ!」
と腑に落ちる。
「HSPだから苦しい」のではなく
「正しい扱い方を知らなかっただけ」
と気づいたことで、
人生が好転しはじめた。
今は、HSPの繊細さを
「弱さ」ではなく「才能」として活かし、
小さな幸せを、
敏感に感じ取れる自分を誇れるようになった。
「一人で抱え込まず、頼ってもいい」
と思える安心感を取り戻し、
自己肯定感と共に
本来の自分らしさを取り戻した。
私の願いは、過去の私のように
「我慢するしかない」と思い込み、
生きづらさに苦しんでいる人に、
少しでも早く気づいてもらうこと。
HSPの気質は、
感じやすさを幸せや喜びに変える大きな力。
限界を迎える前に、
「自分らしく生きる」という
選択肢があることを知ってほしい。
┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
過去の私は「助けて」が言えず、
孤独の中で自分を責め続けていました。
でも今は、HSPの特性を理解し、
潜在意識と向き合うことで
「安心して自分らしく生きられる毎日」
を実感しています。
「変わりたい」
そう試行錯誤してきたあなたなら大丈夫。
我慢や自己否定から抜け出し、
「自分で自分を大切にできる幸せな生き方」を
一緒に育んでいきましょう .*・゚
▼さらに詳しいプロフィールは下記から▼
幼少期から様々な困難を、経験してきました
五感からの刺激に敏感な子ども時代、
周りの大人からはしっかりものと思われる反面、気難しいと思われる・・・
田舎の長女として「しっかり者」「いい子」であることを求められ、自然と我慢や遠慮が普通でした。小学生の頃から人の顔色を読み、空気を察して行動するのが当たり前。
幼少期から暗い場所は嫌いではないものの、閉鎖的な場所、エレベーターや納屋など窓がない所へ行くと、なぜか逃げ場がない恐怖心で息が出来ないくらい苦しくなることがありました。
洋服の繊維にも敏感です。授業中や朝礼などじっとしている時には特にひどく、首や背中は特に敏感で着れない服もありました。それを両親へ言うと「わがまま」と、わかってもらえず悲しい思いをしました。
匂いにも敏感で、雨が降る前の匂いや季節が変わる匂いや空気の重さなど感覚的に感じ取ることができます。
不自由に感じる感覚過敏も多い中、この感覚は昔も今もかわらず心地が良い私の好きな特性です。
一方で、ニンニクやショウガ、香草など食べ物の匂いや、給食で出される魚の匂いや油の臭いがとても苦手でした。保育園の給食で竜田揚げが出た時にはどうしても食べられなくて、毎回泣きながら他の園児がお昼寝が終わるまで教室に1人残されて、先生が溜息をつきながらお盆を下げた悲しい記憶があります。

人との関わりでの疲れやすさ、 幼少期から誰かと一緒にいると疲れる体質でした
子供会で学校の校庭にテントを張ってお泊りをした時、砂で肌がざらつく感覚や汗で肌がべたつく感覚が不快に感じていました。
そのことを両親に話しても「それがキャンプの醍醐味」と言われて、空気を台無しにしている自分に対して罪悪感を抱くこともありました。
また、周りの友達が楽しそうに学年を問わず話しているのを見ると、なんだか自分だけ置いてけぼりになっている感覚がありみんなといるのに孤独を感じていました。
常に誰かと一緒にいる環境の中で、何を話せばいいのか自分がどこにいればいいのか居場所を探している状況にとても緊張していたのを覚えています。
楽しいけど緊張するし疲れる、「早く帰宅時間にならないかな」と時間ばかり気になっていました。
お泊りや誰かと出掛けるとストレスでお腹が張って痛くなることや突然下してしまったりと胃腸が弱い子ども時代でした。

恥ずかしがり屋、過度の緊張と赤面症、言葉への恐怖
保育園の時から、私は赤面症でした。
一度「100円」という発音がおかしいと男子に指摘されてから、自分が話す言葉でまた笑われるんじゃないか?変な子供だと思われているんじゃないかって不安が強かったのを覚えています。
それから近所のおじさんや先生、友達と話す時にもうまく言葉がでず、そんな自分が恥ずかしくて顔から火が出るほど赤くなっていました。
そのことで男子からは「話すとすぐ泣く」と言われて避けられるようになりました。
学校の給食でグループで向き合って給食を取る時にも、食べている動作や音など他の人の様子や自分がどう見られているのかが気になってしまい、食べること自体が恥ずかしさを強く感じていました。
ぬるい牛乳の味も嫌いでこっそり持ち帰ってばあちゃんにあげると喜んでいたのが唯一の救いでした。
大人になってからも会食が苦手だったけど、だんだんとそんなにみんな他人を気にしていないんだなということに気がついてからは食事もラクになりました。

周囲の顔色を常に気にしていた日々
いつも周囲を気にしたり、いつも怖い高学年の人たちの顔色を伺っていました。
小学校は集団登下校だったため、自分が歩くのが遅れたり友達と話していると悪口を言われるのでできるだけ上級生の気に障らないように注意していました。
また急に上級生が友人と別の道で帰ってしまうこともあり、残された下級生と自分たちは事故に合わないよう自分の身を守らなきゃいけないと責任感を持たないといけないと、気持ちが落ち着かないことがあったのを覚えています。

家族の感情を敏感に察知
母が仕事から帰ってくるときの車のエンジン音で母の機嫌が分かりました。ドアの開閉、包丁で料理をするときの音からも母の感情が伝わってきて、なんで怒っているんだろうと疑問を持っていました。
思春期にもなるとそんな母が発する音から、母の感情を感じてはイライラして喧嘩になることもしばしばありました。
父の場合はたばこの煙を吐くときの息の音でも機嫌が分かりました。眉間にしわがある時は要注意、ちょっとしたことで怒鳴られるため部屋にいないようにしようと判断していました。
時々判断をミスることもあり父の逆鱗に触れて説教が始まることがあるのですが、その経験を繰り返さないようにと過去の経験から予測して動いていたと今となっては思います。

いつも心のどこかで消えたい、早く大人になりたいと願っていた幼少期
3人姉妹の長女のわたしは「お姉ちゃんなんだから我慢しなさい」「我儘ばかり言うんじゃない」と、祖父母や両親から言われ続けていました。
「好きでお姉ちゃんになったわけじゃないのに」と理不尽な気持ちを抱きながら、布団の中で行き場のない悲しみや怒りを我慢してた記憶があります。
しかしいくら我慢していても溜まった感情が爆発して、大泣きすることもあります。泣くこと自体が許されなかったので大泣きした時には父の大激怒で「泣き虫!」と説教がはじまります。
わたしは小学2年生の時から早く大人になりたいとずっと思っていました。いつも「我儘ばかり言うな」と言われ続けて、自分の中で何が我儘なのか幼い私には分かりませんでした。
幼いころの経験から、我慢することで自分が否定されなくて済むというルールを幼少期からコツコツ作り上げてきました。
そして自分が26歳で適応障害になるまで、どんなに辛くても、どんなに理不尽でも自分さえ我慢すれば上手くいくというルールを信じて疑いませんでした。
このルールを手放すという選択も我慢しないで上手くいく方法なんて絶対に無理、誰かに怒られる、嫌われるという思い込みが強くて自分が変わる事にも恐怖を感じていました。

救えなかった命と、救えなかった自分――看護師としての挫折と転機
念願の看護師になった私は、ニュースや本で活躍するような立派な看護師になって自分を変えるために東北の田舎町から関東の救急の病院に就職しました。
慣れない都会の生活と新人として覚えることが多くて本当に大変でしたが、それ以上に人間関係が複雑で、先生や先輩から嫌われたら話も聞いてもらえないし失敗したら長時間叱責されるのが当たり前の環境でした。
もちろん命に関わる仕事であり救急の現場なのでミスは絶対に許されません。
だから常に緊張していたし周囲のスタッフの顔色の変化は見逃さないように気をつけていました。HSPだったこともあり、瞬時に顔色を伺って対応することは周りの同期よりも出来ていました。
しかし本当に怖い医師の前では相手の不満や高すぎる要望が分かりすぎるからこそ、そこに達していない自分が余計にダメだとジャッジしてしまい動けなくなってしまっていました。
ある夜間帯でその先生の担当患者さんを受け持った時のことです。
鋭い眼光と怒鳴り声で先生からの指示、緊急手術までの間に患者さんは腹部の激痛のあまりパニックで暴れまわりました。
私は必死に患者さんへ寄り添いながらも医師の指示の処置を同時にこなして、やっと手術の時間を迎えましたが、その患者さんは術中に亡くなってしまいました。
翌日、医師は師長へ術前の私の管理が悪かったから亡くなったと報告しました。私は頭が真っ白になって、もうこの世の終わりだと、看護師なのに患者を救えない私なんて看護師失格だ、生きている価値がないと延々と泣き続けました。
今思えばやることはしっかりやっていたし、どうしようもなかった状況。ただの医師の八つ当たりだと思いますが、当時の私はそんなことを考える心の余裕もなく、自分自身を大切にするための心の器も完全に壊れていました。
仲間や先輩からは優しい言葉をかけてくれましたが、この体験から、私はこんな責任が重い所でダメなわたしなんかがやっていける世界ではないと、3年間務めた病院を転職することに決め、地元に戻りました。
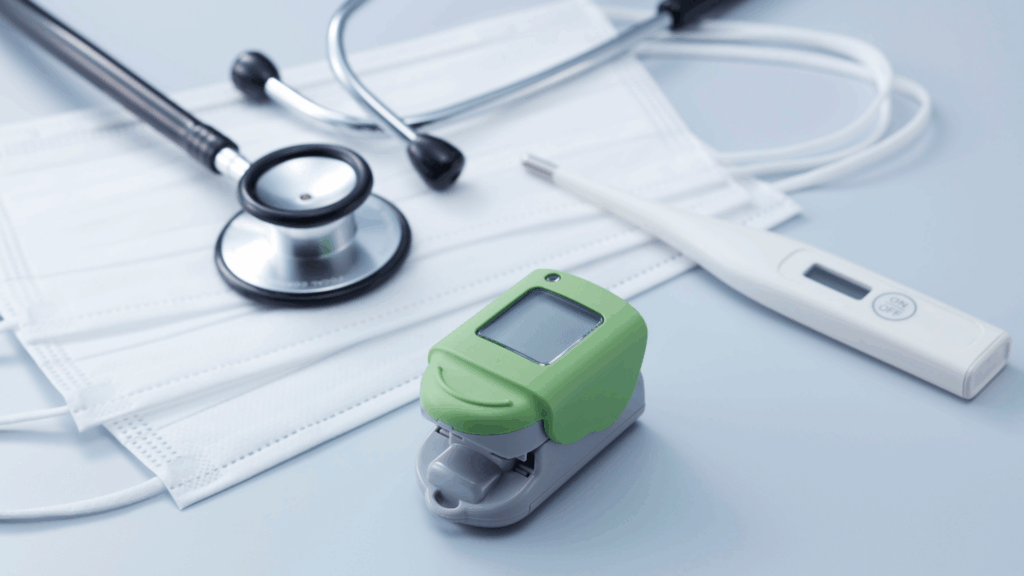
HSPの私が陥っていた思考パターン
私はずっと人の顔色や空気を読むのが得意でそれが普通だと思っていました。
だから「理想の学生」「理想の子ども」「理想の看護師」といった、誰かが望む人物像に合わせるのが当たり前だと感じていたんです。そして、そんな社会の常識に当てはまるように必死に努力してきました。
それは望んでそうしてきたというよりも、そうしないと他人から嫌われてしまう、独りぼっちになってしまう、親から愛してもらえないという恐怖が根底にあったのだと思います。
止めるという選択で、わたしは頑張るだけでは上手くいかないということを学びました。
誰かに怒られて否定されないように頑張ることでいつか認められる、だから頑張ろう、頑張れば報われる。そう自分に言い聞かせてきました。だから本当の自分や気持ちを抑え込んで無理に頑張ろうとして、誰かが掲げる理想の何者かになろうとしていました。
でもそれは、本当の自分のなりたい姿じゃないから、違和感を抱えたまま頑張ろうとしたり無理したため身体や心に不調をきたし、自分本来の良さだったり培ってきたパフォーマンスを発揮できませんでした。
自分が叱責されるのが当たり前の環境にいると、それがオカシイということに気がつかなくなります。
そしてどんどん自分を貶していくため自分自身の自信もなくなってしまうし、安心感や自分の好きという気持ちにさえ気づけなくなります。
なぜならそんな感情を抱いていても頑張れない、恐怖があるからそれを解消するため行動が最優先となってしまうからです。だからいつまでも恐怖で支配されたラッドレースから降りられないのです。

いつも疲れやすいのは、根性がないからだと思っていました。
看護師時代は人間関係で苦労しました。でも顔色や雰囲気、匂いの変化や手の触覚で患者さんの状態が感覚的にすぐにキャッチできました。入院中の脳梗塞の早期発見やオペ後の容態変化をいち早く発見したり、でもそれが気に食わない先輩もいました。
「あなたといると荒れるから嫌」と心無い言葉を言われたり。
だから余計に顔色を伺ったり下手にでたりと‥‥
刺激に敏感だから変化をすぐに察知できる能力、予測できる能力の高さと、それをキャッチした後に処理するエネルギー消費量がものすごく多かったから疲れやすかったんだなと、HSPに気づいた今ならわかります。
だから、仕事以外は寝てすごすことが多くありました。もちろん、自分のことはあと回し、1人暮らしの家の中はいつも散らかっていました。
確実にセルフネグレクトだったと思います。他人を優先しないと価値がない、この信念でずっと生きてきていました。

優しい人でありたいのに、どうしても感情が抑えられない苦しみ
わたしは他人の顔色を伺って自分の気持ちを抑え込む反面、どうしても感情が抑えきらなくなる事がありました。
それは仕事で自分はすごく頑張っているのに、手を抜いている人や新人の時の自分よりも努力をしていないような後輩に対してどうしても優しくできなかったのです。
周囲からは頑張り屋で優しいと言われる反面、
後輩指導となると「なんで出来ないの?」「どうして勉強してこなかったの?」とイライラを抑えることが出来ないのです。
わたしの指導の後に涙を流す新人を見て、ふと我に返り傷つけてしまった申し訳ない事をしたと後悔する反面、私だってそうやって育てられてきて我慢してきたのに簡単に泣くなんてと怒りも込み上げてきました。
この『いい人でありたい』という気持ちと、『なんで頑張れないの?』という気持ちの葛藤は、自分自身の心の投影だったと冷静になった今ならわかります。
でもちゃんと指導もできない、ちゃんと後輩も育て上げられない、そんな頑張れない自分には価値がない、という価値観に縛られていました。

この価値観は後輩指導だけではなく、幼い我が子や信頼している夫に対しても同じでした。
わたしを選んで生まれてきた可愛い我が子なのに、保育園から家に帰る車の中から延々と泣き叫んで「ママ抱っこ~」と甘えてくる。
でも頭の中は『もう時間がない!家事が出来ない!次の日のために早く寝かせないと、みんな体力が持たない!早くしないと!』
という思考が強く、
「何もできないじゃない!いい加減にしてよ!」と2歳の子どもに対して怒鳴ってしまうことがありました。
怒鳴った後の恐怖で更に泣き叫ぶ息子の顔を見て、罪悪感でいっぱいになりわたしはダメな母親だと自分を責めました。もうこんなことはしないと思っても、気持ちが焦ったり仕事でミスをしていっぱいいっぱいになると、どうしても感情のコントロールができなくなり、子どもや夫にキツく当たってしまう。
本当はもっと笑顔で温かい理想の家族を求めていたはずなのに、自分の手で壊している自分が憎い、でもどうしても我慢できないこんな葛藤を抱き、自分自身が嫌いでした。
「ちゃんとできる自分」でいるために、いつも心が追われていました。
だから、「それを阻むものは許さない。こんなに頑張っているのに、認められないなんて酷い!」と感情を出せる相手を選んで無意識に攻撃していました。余裕も安心感も感じることすら制限をしていたんだと思います。
この時期の私は、HSPとしての感受性の高さが裏目に出て、自分の感情に振り回されるだけでなく、愛する人まで巻き込んでしまっていました。そして、そんな自分を受け入れることができず感情をコントロールできない自分は欠陥品なんだと自分自身を否定し続けていました。

「自分なんかが…」と、いつも遠慮して生きていた
美容室の予約をするだけで、相手の反応を予測していつも緊張してしまい美容室に行くことが嫌いでした。予約の電話をするだけでも時間帯や相手の状況が気になって、受付の方の声のトーンが低いと「迷惑な客と思われているかも」と感じ、自分のタイミングの悪さを責めて電話をした自分を後悔していました。要望を伝えるだけでも、「どうせ似合わないと思われていたらどうしよう」なんて思ってしまい、髪型の希望を聞かれても、「こんな私が細かい注文なんてしていいのかな」と遠慮してしまいます。
施術中も、美容師さんの表情が気になって仕方がありません。
会話にも気を遣ってどう思っているのかなど考えては、美容師さんの姿を鏡で見ることも怖くて早く終われーと思っていました。帰り道は、自分の返事ひとつにも反省が止まらずどっと疲れてしまい、もう行きたくないなと…結局、毎回違う美容室をホットペッパーで探していました。

お願いができない
相手の状況が分かるからこそ忙しい相手に対して
「お願いしたら負担だよね」「もう少し後で話した方が良いかも」と相手の顔色ばかり気にしてしまい、言わなきゃ!とは思いつつも、タイミングばかり見計らっては逃し、気づけばもう夕方となることもしばしばありました。いろいろタイミングを考えて伝えたのにも
「もっと早く言ってくれればよかったのに」と言われてしまうと、「なんで勇気をもってあの時言えなかったんだろう」と考えすぎた過去の自分を後悔しては落ち込んでいました。

ミスで世界が終わるような絶望を感じる
小さなミスでもこの世の終わりかのように、激しく落ち込みやすい自分が本当に嫌いでした。職場でメールの宛先を間違えただけで「やってしまった…」「なんて私はダメな人間なんだろう」って激しく自分を罵倒していました。すぐに謝罪して、周りが「気にしすぎだよ」って声をかけてくれても、「やっぱりわたしって本当にダメなんだ」って自分を否定する言葉が頭から離れません。夜寝る前やふとした時にまた思い出しては、ミスのことを考えて落ち込んで「周りと同じようにできない自分」が嫌でした。

自分がHSPだと気づき、自分を好きになるチャンスが訪れる
そんなとき、信頼できるHSP専門の先生との出会いがありました。
そこで初めて、ずっと抱えていた「生きづらさの根っこはHSPの使い方にあったんだ」と腑に落ちたのです。
「HSPだから生きづらい」のではなく、
「HSPという気質をどう扱うか」が人生のカギだった――
そう気づいた瞬間、ずっと自分を責めてきた心がスッとほどけていきました。
もちろん、すぐに劇的に変わったわけではありません。
「人に頼るなんて迷惑じゃないか?」
「弱音を吐いたら嫌われるんじゃないか?」
そんな思い込みを手放すには、時間も勇気も必要でした。
でも少しずつ、先生のサポートを受けながら「頼ってもいい」「助けてって言ってもいい」と思えるようになり、
一人で抱え込まず、人と分かち合う安心感を知りました。

今の私の変化
過去の私は、幼少期からずっと不安と自己否定に追われていました。
でも今の私は、違います。
HSPの気質を「短所」ではなく「強み」として受けとめられるようになり、
「感じやすい自分だからこそ、自分の幸せのために使える」と思えるようになったのです。
例えば、
・小さなことにも幸せを感じられる感受性
・人の痛みに深く共感できる優しさ
・物事を丁寧に見つめられる集中力
以前は「生きづらさ」になっていたものが、今では「私らしさを輝かせる才能」になっています。
過去の私のように、ひとりで抱え込み、悪循環のループから抜け出せなくなる前に──。
限界を迎えて心や体を壊してしまう前に、「助けてもいい」「頼ってもいい」と気づいてほしいのです。

HSPは病気ではありません。
人より感受性が強いからこそ、苦しみや悲しみに敏感な一方で、喜びや楽しさ、幸せを人一倍感じられる才能を持っています。
大切なのは、その力を「自分を苦しめるもの」として使うのではなく、
「自分と人を幸せにする力」として活かしていくこと。
そのためには、まずは自分が幸せであることが一番の土台です。
人との境界線を知り、他人に振り回されずに「自分の人生」を生きてほしい。
そして、あなたの中に眠っているHSPの才能を、自己肯定感を高めるエネルギーへと変えていってほしいと願っています。
今の私は、HSPの気質を受け入れ、繊細さを強みに変えて生きることができています。
敏感さがあるからこそ、小さな幸せに気づけるし、人の気持ちに寄り添える。
HSPで生まれてきたことを「よかった」と心から思えるようになりました。
だからこそ、私は一人でも多くのHSPさんが「この気質を持って生まれてよかった」と思えるように、全力でサポートしていきたい。
これが私の使命であり、カウンセラーとして活動する根底の願いです。
長文を最後までお読みいただき、ありがとうございます^^
もし同じように悩んでいるなら、まずはお気軽に体験カウンセリングでご相談ください。
あなたの人生が少しでも前に前進できるきっかけになれるかもしれません。